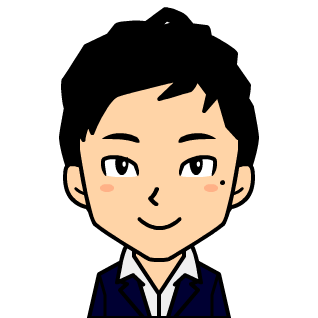借金したまま死亡したらどうなるのか?

もし消費者金融に借金を残したまま死んでしまったらどうなるのでしょうか。
やはり家族に請求がいくのでしょうか。それとも払わなくてよくなるのでしょうか。
家族には内緒なので、万が一自分が亡くなっても、出来れば残った家族に負担をかけたくないと思っている人は多いのでこれは結構重要な問題です。
では詳しく解説していきましょう。
Contents
借金は相続の対象となる
まず基本的なこととして、「借金は相続の対象になる」ということを覚えておいて下さい。
一般的な相続のイメージは、財産などの「プラスの権利の相続」という印象がありますが、借金も「マイナスの義務の相続」として立派な相続の対象になります。
このため、借主が死亡してしまった場合、基本的には相続人が相続して借金を引き受けることになります。
そして相続する順位や配分は以下のようになっています。
●第一順位:子
(配偶者1/2・子1/2)
●第二順位:直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)
(配偶者2/3・直系尊属1/3)
●第三順位:兄弟姉妹
(配偶者3/4・兄弟姉妹1/4)
※配偶者は常に相続人となる
※配偶者以外の者は、配偶者とともに次の順位で相続する
もちろんこの順位は、借金だけでなく、一般的な財産相続も同じです。
様々な相続方法
このように借金も相続の対象となっていますが、現実的には、マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまったり、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかはっきりわからなかったりなど、様々な状況が想定されます。
そのため、様々な状況に対応出来るように法律では、次のような、承認、放棄の方法が定められています。
①単純承認
単純に権利も義務も全て相続すること。(プラス財産が多い場合に対応)
②限定承認
相続で得た財産の限度でのみ、被相続人(亡くなった人)の債務(借金)を弁済するという条件で権利と義務を承継すること。(プラス財産、マイナス財産どちらが多いかはっきりしない場合に対応)
③相続放棄
権利も義務も全部放棄すること。(マイナス財産が多い場合に対応)
知らないうちに借金を相続してしまうことはあるのか!?
相続人は、相続開始を知った時から3カ月以内に承認か放棄をしなければなりません。
この期間を経過した場合は「単純承認」したものとみなされてしまいます。
「知った時から3か月以内」というきまりがあるので、消費者金融は借金を引き受けてもらうためには「故人に借金があったことを相続人に知らせる」必要がでてきます。
通知したことを立証するために、消費者金融は、相続人への通知を「内容証明」等で行うのが一般的です。
※参考
「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」の起算日は、「相続財産は親などの死亡時に全て把握すべき」という旧時代の考え方に基づき、従来は「被相続人の死亡時」とする解釈が有力でした。
しかし、2019年8月9日に、最高裁第二小法廷で、起算日を事実上、「相続を承継した事実を知った時」にすべきという判決が下りました。
現代は家族構成も多種多様で、親族間の繋がりも減っているので、遺産状況をなかなか完全に把握することは困難です。
そのため事実を知らない相続人に過度な負担をかけないとした判決として評価されています。
そのため相続人の知らないうちに勝手に借金が相続されていたということは、通常ありませんが、内容証明などを受理してしまったら、相続の開始を知っていたとみなされてしまう可能性もあるのでご注意下さい。
消費者金融に生命保険はないのか
同じローンでも、住宅ローンなどの高額ローンには「死亡保険」がついているのが一般的です。
では消費者金融にこのような保険制度はないのでしょうか。
結論から言えば、現在、消費者金融でこのような保険を利用している会社はほとんどありません。
かつては消費者金融も、死亡した場合や一定の高度障害状態になってしまった場合に保険金で借金を弁済してくれる、「消費者信用団体生命保険」に加入している会社が多くありました。
しかし、自殺を原因とする保険金の受け取りも多く、返済出来ない人を自殺に追い込んで回収しているとの社会的批判を受ける結果になってしまいました。
そのため現在の貸金業法では、自殺を原因とした生命保険契約は原則禁止されています。
もちろん今でも自殺を保険事故としない生命保険契約については締結しても違反にはなりませんが、生命保険を採用している消費者金融はほとんどなくなってしまいました。
過払いというプラスの財産!?
一見、ただの借金で「マイナスの財産」と思っていたものが、思わぬことで「プラスの財産」に変わることもあります。
グレーゾーン金利時代(2010年6月17日以前の契約)に、長年、消費者金融と取引があった場合は、利息制限法の金利に引き直し計算をすると、利息を払い過ぎている「過払い状態」になっている可能性もあります。
本人が死亡してりる場合は、この過払い金返還請求を相続人が行うことも可能です。
このようにマイナス財産と思っていたものがいわゆる「過払い」によって、プラスの財産に転じることもあるので、故人の取引が長そうであれば、弁護士など専門家へ相談することをおすすめします。
ご家族が亡くなった場合の対応方法
ご家族が亡くなった際、故人に借金の可能性がある場合は、相続人が信用情報期間に開示請求をして、借金の全容を調査することを強くおすすめします。
また、借金の全容を把握しないまま、一部の業者だけに支払いをすることは控えるべきです。
尚、開示請求については各信用情報機関のHPで確認することができます。
そこで故人の借金が少なからず登録されていた場合、故人に何ら「プラス財産」が存在しなければ相続放棄をすればよいだけですが、そうでない場合に相続をどうすべきかについてはやはり弁護士などの専門家に相談する方が無難です。